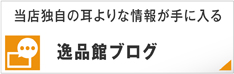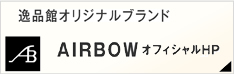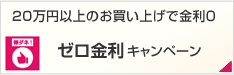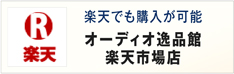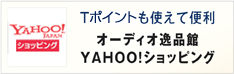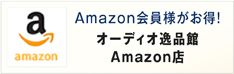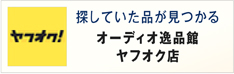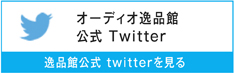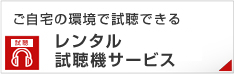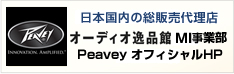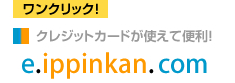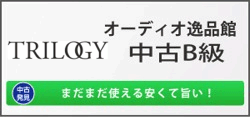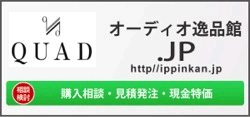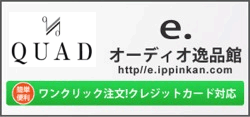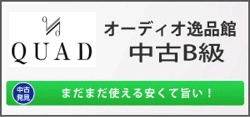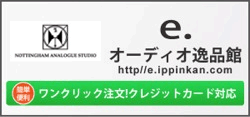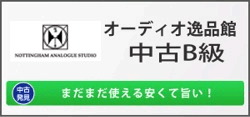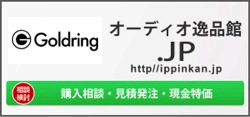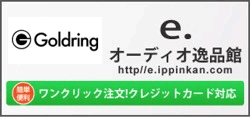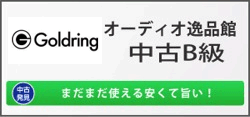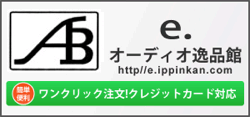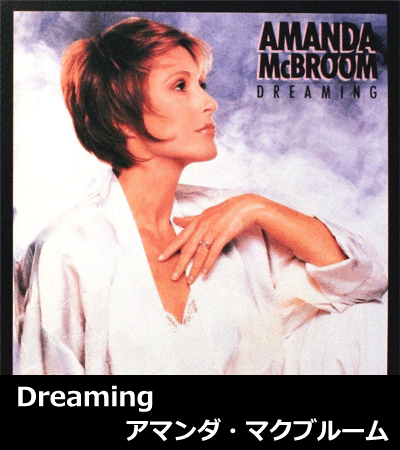■各種コンテンツ
■サービス・キャンペーン ■逸品館運営・外部ショップ ■Twitter・Facebook ■試聴機レンタルサービス ■オーディオ逸品館 MI事業部
オフィシャルサイト
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
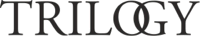 TRILOGY(トリロジー) 906/907
Phono Stage
TRILOGY(トリロジー) 906/907
Phono Stage
 QUAD(クォード)
QC24P 真空管式フォノイコライザーアンプ 音質比較テスト
QUAD(クォード)
QC24P 真空管式フォノイコライザーアンプ 音質比較テスト
イギリスの比較的新しいオーディオメーカー「TRILOGY(トリロジー)」の日本での取り扱いが始まりました。輸入代理業務は、「SON」が行います。
日本の公式ホームページはこちら ・ 英国の公式ホームページはこちら
TRILOGY社の社長兼メインデザイナーをつとめる「Nic
Poulson」は、BBCで放送エンジニアとして働いた後、英国の主要空港の着陸誘導システムのデザインや、最近人気の高いオーディオ電源コンディショナー「ISOTEC」の設立を経て、1991年にTRILOGY社を設立しました。
・TRILOGY製品リリース
1991年
TRILOGY AUDIO設立
1992年
901:真空管プリアンプ、948:50W真空管パワーアンプ、958:100W真空管パワーアンプ、発売。
1994年
902:真空管プリアンプ、918:リファレンス真空管プリアンプ、発売。
1995年
900:真空管プリアンプ、904:フォノステージ、905:真空管MCヘッドアンプ、発売。
2001年
RC211:リファレンスモノラル真空管パワーアンプ、発売。
2008年
909:真空管プリアンプ、968:60W真空管パワーアンプ、990:100Wハイブリッドパワーアンプ、発売。
2011年
909/990を大幅にアップグレード、907:フォノステージ、発売。
2014年
925:ハイブリッドプリメインアンプ、発売。
2015年
931:ヘッドフォンアンプ、906:フォノステージ、発売
2016年
903:真空管プリアンプ、993:125Wハイブリッドパワーアンプ、発売。
今回は豊富な商品構成の日本市場に投入された製品から「906 フォノステージ」と「907フォノステージ」の二つのトランジスター式フォノイコライザーアンプを真空管式フォノイコライザーアンプのQUAD QC24Pと比較することにしました。
比較テストの概要をYouTubeで見られます。
製品の概要をYouTubeで見られます。
![]()
最近、アナログレコードがブームです。けれどアナログレコードはCDが登場する直前の1980年にピークを迎え、そこからは急速に衰退しましたから、最近の若い人たちは「レコードの仕組み」と「デジタルとの違い」を知らないかも知れません。そこで、簡単に「レコード」の構造をおさらいしておきましょう。
・レコードの仕組み
レコードは、ディスクに刻まれた溝に音を「振幅」として記録し、それをカートリッジでトレースして電気信号に変換して音楽を再生します。ステレオレコードでは、左右の溝にそれぞれ「右側と左側」の音声が記録されています。
レコードの再生は、ディスクの溝に刻まれた振幅をカートリッジで拾い、それを電気信号に変換しますが溝に刻まれている振幅が小さいため、とても「小さな電圧」しか得られません。増幅機能を持たないレコードプレーヤーが出力する電圧は、1μV前後でCDプレーヤーから出力される電圧の1/1000程度しかありません。
また、低音はそのままの音量では溝が深くなりすぎてレコードが壊れてしまうので、低い音の音量が小さくなるような「イコライザーカーブ」を使って、音が記録されています。
詳しくはこちらのWEBページをご覧ください(ファイルWEBへのリンク)
・レコードを聞く方法
レコードプレーヤをCD入力(ライン入力)に繋いでも「小さな音しか出ない」、「低音が出ない」のは、CDプレーヤーが出力する信号とレコードプレーヤーが出力する信号の「大きさ」と「周波数特性(イコライザーカーブ)」が違うからです。
このためレコードを聞くには「フォノイコライザーアンプ」という、専用のアンプが必要です。
・フォノイコライザーアンプの仕組み
「フォノイコライザーアンプ」には、カートリッジ(レコードプレーヤー)から出力される小さな信号を増幅するための回路と、RIAAカーブという特殊なイコライジングを行う回路が搭載されています。アンプの中にこの回路が組み込まれている場合、「フォノ入力」という端子が備わりますが、アンプに専用の端子が備わらない場合、レコードを聞くために「フォノイコライザーアンプ」が必要になります。「フォノイコライザーアンプ」を通過したレコードの音は、CDプレーヤーから出力される信号と同じになりますから、フォノイコライザーアンプはアンプの「CD/ライン入力」に接続します。
しかし、アンプにフォノイコライザー回路が内蔵されていても、カートリッジの小さな信号を増幅するための回路は、アンプ内蔵よりも「別置き」にするほうが音質的に有利なので、さらに良い音を聞くためには専用端子が備わっていても「フォノイコライザーアンプ」が必要になります。今回テストする「TRILOGY」や「QUAD」の「フォノイコライザーアンプ」を使った場合も、アンプに備わっている「フォノ入力」よりも音が良くなります(高価なプリアンプなどはその限りではない場合もあります)。
![]()
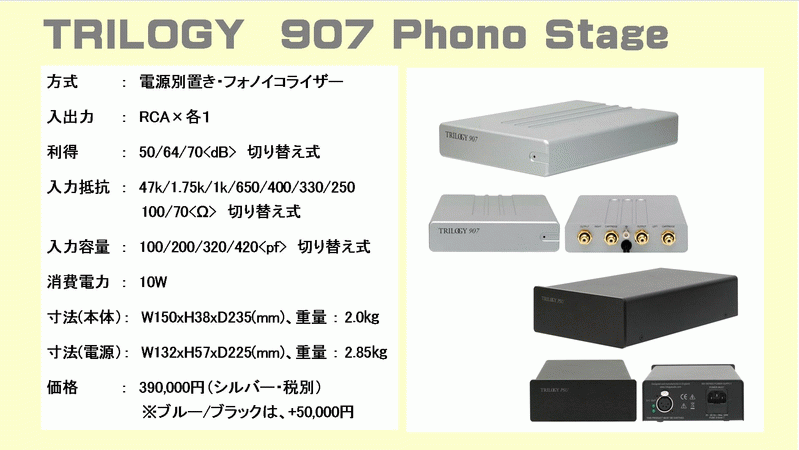
TRILOGY(トリロジー) 907 フォノイコライザーアンプ メーカー希望小売価格 \390,000(税別)
|
・907
Phono Stage の概要
Trilogy 907 Phono Stageは、高性能ターンテーブルと高性能HiFiアンプの性能を生かし切る、完璧なインターフェースとなるように設計されています。Trilogy
907は、最高レベルの音楽再生のために精密に作られ、あなたのレコードから生き生きとした音楽を再現します。
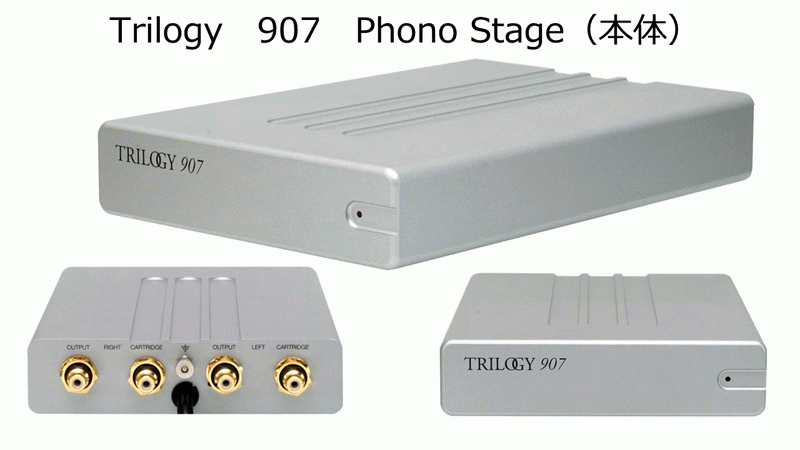
・筐体設計
907の筐体は、アルミニウムの固体ビレットから削り出された継ぎ目のない箱形状です。NC加工された1.5kgの継ぎ目のない筐体は、高い強度による優れた制振性と理想的なアース接続を実現します。電気的に繋がった継ぎ目のない筐体は、微弱な信号を増幅するフォノアンプのS/N比の向上にに大きな力を発揮します。

・電源部
907のために開発された電源部の平滑コンデンサーには、現在最も高音質な「Mundorf(ムンドルフ)」が使われ、ISOTEC社を設立した「Nic
Poulson」の才能により、通常の電源よりもローノイズで、強力な電源供給能力が与えられています。刻一刻と変化する音楽信号をありのままに増幅するための十分な能力が与えられたこの電源部を増幅回路と別筐体にすることで、電磁誘導によるノイズの低減も実現しています。
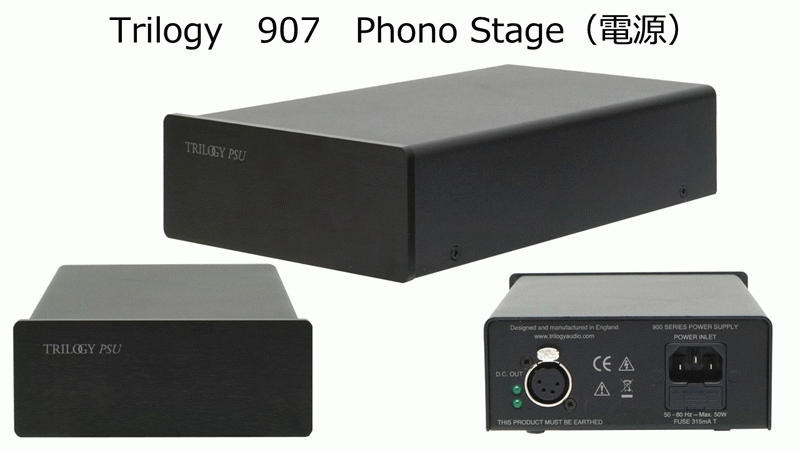
・増幅回路
907の各回路には、高精度ペアマッチングされた入力トランジスタが使われ、フィードバックを使わない無帰還回路で高帯域幅と低歪みを実現しています。それぞれの回路は、完全な左右独立構成とされ、クロスオーバ歪み(クロストーク)が排除されています。
RIAAのイコライゼーションには、パッシブフィルターが採用されています。フィルターに使われるパーツは、精密に測定されマッチングされています。
MMまたはMCのゲイン設定とカートリッジのロードは、裏面にあるディップスイッチを使って、細やかに調整が可能で、あらゆるタイプのカートリッジとの精密なマッチングを可能としています。

![]()
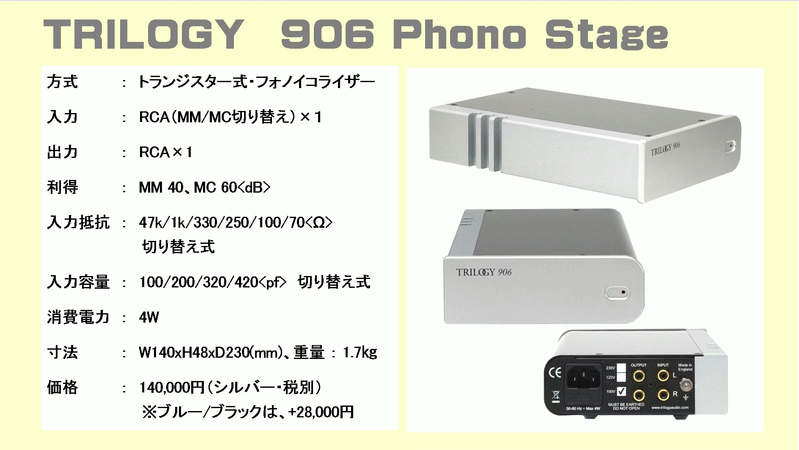
TRILOGY(トリロジー) 906 フォノイコライザーアンプ メーカー希望小売価格 \140,000(税別)
|
・906
Phono Stage の概要
高い評価を得た907フォノステージの音質をより低価格で実現するため、907の技術を可能な限り採用しながらコストダウンを行ったモデルとして開発されたのが、Trilogy
906 Phono Stageです。このモデルは、最高クラスのフォノイコライザーの性能と本物のオーディオファイルの期待に応えられるパフォーマンスを、より手頃な価格で実現するために開発されました。
しかし、コストの制限を受ける製品でパフォーマンスを高く維持し、コストを低く抑えるには、本当の意味でのスキルと経験が必要です。パーツ点数が少ない906の各コンポーネントは、より高い性能を実現するため、TRILOGY社の社長兼デザイナー「Nic Poulson」によって慎重に評価され、開発され、精査され、906で実現できる最高の性能を発揮するように設定されています。
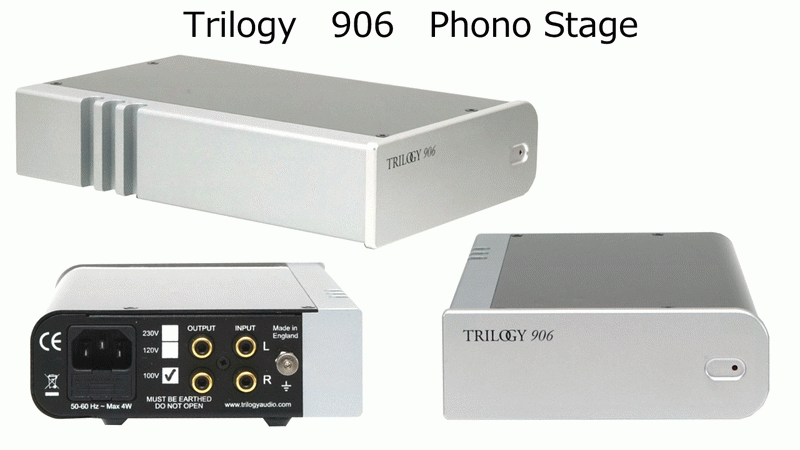
・フルディスクリート回路・高音質パーツの採用
906の増幅回路には、安価で既製のオペアンプ集積回路は使われません。すべての回路は、シングルエンドのクラスAのディスクリート回路が使われ、907と同じく完全負帰還(ノン・フィードバック)の純A級回路で、高帯域幅と低歪みを実現しています。
RIAAイコライザー回路には、パッシブ型のイコライゼーション回路が使われますが、そのパーツは907同様に精密に測定されて組み込まれています。
DCサーボの採用により出力コンデンサーが取り払われた出力回路は、抜けの良い高解像度な音質を実現します。
・幅広いカートリッジとマッチングが可能
MMまたはMCのゲインとローディングの設定は、裏側にあるディップスイッチの設定で可能です。907では完全モノラル回路の採用により、設定スイッチは「左右独立」でしたが、ステレオ回路が使われる906では左右が統合されています。カートリッジロードは、70オームから47Kオームの抵抗値と、100から420ピコファラッドまでの4つの容量値が選択でき、幅広いカートリッジに対応しています。
・カスタムメイドのトロイダルトランスと独自の回路で構成される電源部
低ノイズでリニアな電源供給能力を実現するため、カスタムメイドのトロイダルトランスを使う電源部は、高品質オーディオパーツが使用され、クラスを超える贅沢な構成となっています。また、906の電源部も優れた電源コンディショナー「ISOTEC」を設計した「Nic
Poulson」の巧みな設計により、通常の電源よりもローノイズで優れた過渡特性が与えられています。
・イギリスでハンドメイドされています
906は、すべてイギリスでハンドメイドされ、他のすべてのTrilogy製品と同じ高水準に仕上げられています。
![]()
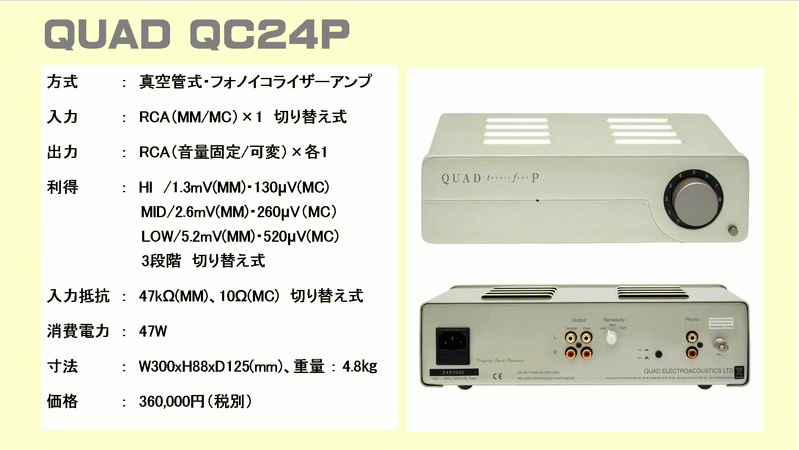
QUAD(クォード) QC24P 真空管式 フォノイコライザーアンプ メーカー希望小売価格 \360,000(税別)
|
・QC24P
真空管式フォノイコライザーアンプの概要
QUAD QC24Pは、真空管設計の鬼才、EARの創立者である「パラビチーニ氏」によって設計された、真空管式フォノイコライザーアンプです。
電源部にはトロイダルトランスとトランジスターを使った整流回路が使われ、増幅にはミニチュア管「Philips
6111」が各チャンネル2本、合計4本使われます。ゲインは、3段階の切り替え式が採用され、MC昇圧トランスを内蔵します。
出力は、RCA(固定出力)の他に、フロントパネルに取り付けられた大型のボリュームの操作によって音量が変えられる「可変出力」が備わり、パワーアンプをダイレクトに接続できます。
![]()
・比較試聴の概要
今回の比較試聴は、レコードプレーヤーに「Nottingham
Interspace HD」、カートリッジにMC型の「Goldring EROICA LX」を使って行いました。
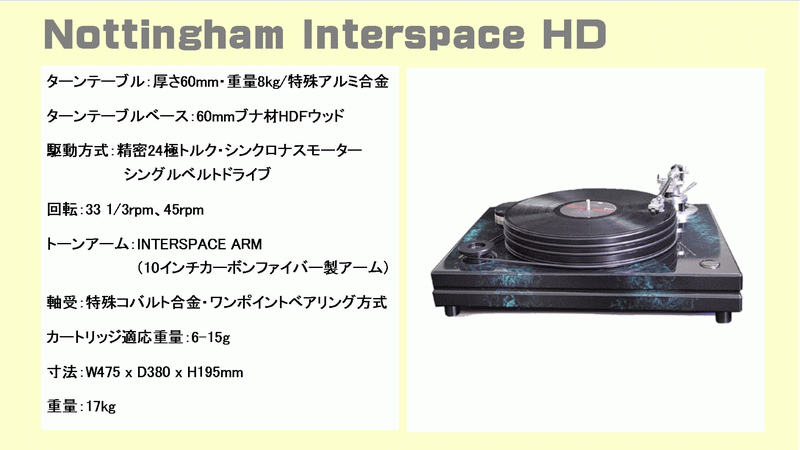
Nottingham(ノッキンガム) Interspace HD メーカー希望小売価格 生産完了モデル
Nottingham(ノッキンガム)製品のご購入お問い合わせは、経験豊富な逸品館におまかせください。 |
||||||
|
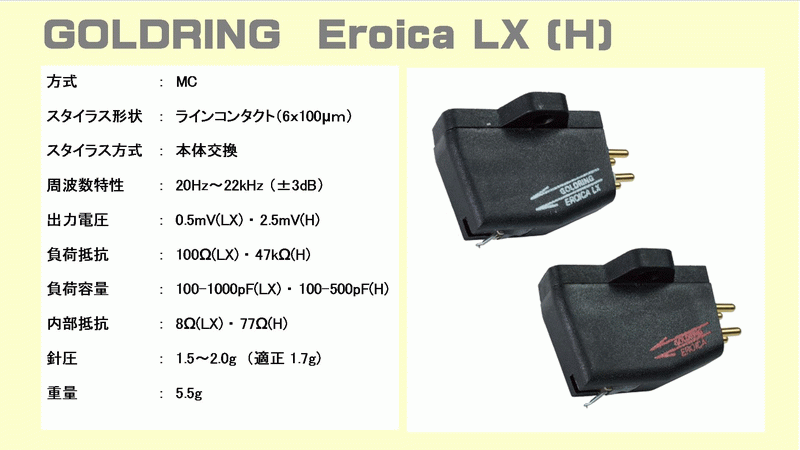
Goldring(ゴールドリング) EROICA LX メーカー希望小売価格 105,000円(税別)
Goldring(ゴールドリング) EROICA H(高出力型) メーカー希望小売価格 115,000円(税別)
Goldring(ゴールドリング)製品のご購入お問い合わせは、経験豊富な逸品館におまかせください。 |
||||||
|
QUADの試聴は、内蔵するMCトランスを使った場合と、外付けの昇圧トランス「AIRBOW BV33」を併用した場合も比較しました。
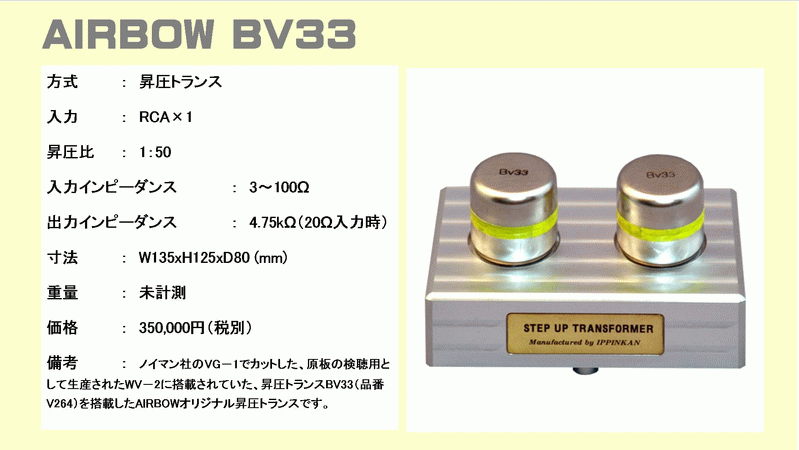
AIRBOW(エアボウ) BV33(昇圧トランス) メーカー希望小売価格 350,000円(税別)・ 限定生産品
AIRBOW(エアボウ)アナログ製品のご購入お問い合わせは、経験豊富な逸品館におまかせください。 |
||||||
|
 Vienna
Acoustics Beethoven Concert Grand(T3G) (現金で購入)・(カードで購入)・(中古で探す)
Vienna
Acoustics Beethoven Concert Grand(T3G) (現金で購入)・(カードで購入)・(中古で探す)
 AIRBOW
SA11S3 Ultimate (現金で購入)・(カードで購入)・(中古で探す)
AIRBOW
SA11S3 Ultimate (現金で購入)・(カードで購入)・(中古で探す)
試聴したソフトは、音の良いレコードから選んだ3曲です。ジャズ、電気楽器を使った女性ボーカル、交響曲を聴きました。
YouTube動画へのリンク ※
各フォノイコライザーから出力された信号は、アンプやスピーカーを使わず、ラインレベルのままダイレクトにA/D変換しています。 LA4「亡き王女のパヴァーヌ」の比較テストをYouTubeで見られます。※CDプレーヤーとの比較あり。
峰純子「ジェシー」の比較テストをYouTubeで見られます。※レコードのみの比較。
交響曲「展覧会の絵」の比較テストをYouTubeで見られます。※レコードのみの比較。
アマンダ・マクブルーム「Dreaming」の比較テストをYouTubeで見られます。※CDプレーヤーとの比較あり。
ウインドベルの音は透明感が高く、高音がすっきりと伸びていますが、角が立ちすぎることもなく、響きも美しく、純A級無帰還ディスクリート回路の素直な音の良さが感じられます。
ピアノは少しアタックが弱く、やや離れた位置で聞いているようなイメージです。
冒頭部分でのS/N感が高く、金管楽器とリスニングポジションの「距離感」や「コンサートホールの空間表現」が実に見事です。 イントロ部分のシンセサイザーの重量感がしっかりと再現されます。アマンダ・マクブルームの声の「太さ」も良く出ます。伴奏とボーカルの分離感も秀逸で、透明感の高い濁りのない音です。
総合評価 907の音は、906と全く同じです。いいえ、906が後に作られたので、906が907と全く同じという言い方が正しいでしょう。
ピアノのハンマーが弦に当たった瞬間の「アタック(打鍵感)」がきっちり再現されます。
演奏の表現すべきものは906と907で完全に一致します。けれど、細部の音の質感が向上し、密度感も向上することで、907ではコンサートホールがより上質になり(座席の位置が良くなり)、楽団員が増えた(楽器の数が増えた)ように感じます。 イントロ部分のシンセサイザーの透明感と色彩の鮮やかさ、アマンダ・マクブルームの声の迫力が一段と引き立ちます。アマンダの声は「美空ひばり」に少し似ているところがあると思うのですが、そういう本物の歌手が持つ「迫力」が際立ってきます。シンセサイザーの響きも、より長く尾を引くようになりました。 総合評価 イントロのウインドベルの「密度感」では、907がQC24Pに勝ります。フルートやドラムの「密度感」も同じです。QC24Pの魅力は、真空管+昇圧トランスが持っている「ある種のオーバドライブ感」です。 ピアノの「打鍵感」は、907とほぼ同じイメージです。ボーカルは、色彩感がわずかに濃く、峰純子さんの「息づかい」まで伝わるようです。 イントロ部分の金管楽器の音に「演奏者の唇の動き」のようなものが感じられるようになります。弦楽器も、奏者の弓を動かす感じが見えるようです。 また、この曲でも真空管と昇圧トランスを使った「オーバドライブ感(響きの演出効果」で、演奏の主題や躍動感が強調されて聞こえるのが、上手くいっているのでしょう。QC24Pで聞く方が、私にはなんとなく、よりリアルに聞こえます。 イントロのシンセサイザーの音が軽やかです。アマンダ・マクブルームの声もさわやかで、年齢が10歳くらい若く感じられます。私は生でこの曲を聴いていないので判断できませんが、907もQC24Pも、どちらの音も「本物」に聞こえます。ただ、録音の良いこのレコードでは、907の持っている「圧倒的なHiFi感(質感の高さ)」をより魅力的に感じます。 ライブ演奏の楽しさは、QC24Pがより良く演出し、優秀録音盤の質感の高さは、907が上手くそれを引き出すようです。 昇圧トランスを内部からBV33に変えるだけで、楽器の音の質感が俄然向上します。フルートやドラムの音の密度感、質感が向上します。ドラムの重量感、ブラシの鮮やかさ、ウッドベースの断弦感などのアタックが、音の立ち上がりの早さの改善で向上します。 内蔵の昇圧トランスでは、密度感が907にやや劣るように感じましたが、BV33を使うと密度感が向上し907に匹敵するようになります。また、内蔵トランスで感じられた「誇張感」も無くなります。 イントロのピアノの音が「本物」らしくなりました。ピアニストのタッチは、内蔵トランスの方が際立ったように思いますが、ボーカルとのマッチング、ウッドベースとのマッチングが向上し、演奏の一体感が群と濃くなります。 やはり、良い意味で「普通の音」になります。違和感がなく、生演奏を聞いているイメージです。 意外なことに、BV33のもつ癖のなさと質感の高さが、この曲にぴったりとマッチします。 完璧です。 総合評価 2017年2月 逸品館代表 清原裕介 ![]()


フルートの音色も優しく、フルートが木管楽器のように柔らかく鳴りますが、本来上質なフルートはこういう柔らかな音が出ますから、この音で良いと思います。
ベースの音も柔らかく当たりが良いのですが、低音は少し膨らみます。デジタルと比べるとアナログの低音はどうしても少し緩いのですが、それを考慮すれば十分に合格です。
バスドラムの音、ブラシの音もリアルです。低音は怒濤のように・・・、とは生きませんが量感質感共に十分で、しっかりと低いところまで伸びています。
ギターは、断弦しているところ(アタック)の衝撃音がもう少し欲しいですが、胴の木の響きの美しさと弦の乾いた感じの対比がきちんと再現されています。
オペアンプを使うイコライザーアンプとはひと味違う、雰囲気の濃い、明るく優しい音で「亡き王女のパヴァーヌ」が鳴りました。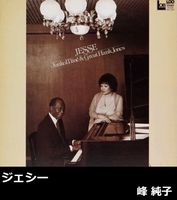
ボーカルは、優しく女性らしい艶と、峰純子さんらしいふくよかさがしっかりと伝わります。
ウッドベースは音程が低く、お腹に響く重量感があります。
「亡き王女のパヴァーヌ」でも感じたのですが、906の良さは「リズム感(タイミング)」です。楽器やボーカルの時間軸の整合性が抜群で、音楽多驚くほどスムースでリズミカルに聞こえます。
このシームレスな滑らかさは、デジタルではなかなか出ないものです。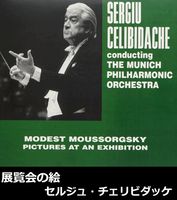
楽器とリスナーの距離が離れている交響曲では、ジャズのように「楽器のアタック」がそれほど強く出ないので、906の柔らかさや響きの美しさ、なによりもノイズの少なさが生きてきて、実にリアルに交響曲が再現されます。
電源一体の小型フォノイコライザーアンプですが、大型電源を搭載するフォノイコライザーアンプのように、しっかりと重量感のある低音が再現され、管楽器のエネルギー感も十分です。
音の密度はさすがに、50万円クラスの高級フォノイコライザーアンプよりもわずかに薄いのですが、S/Nの高さ(バックグラウンドノイズの低さ)に助けられ、聞き取れないようなかすかな音、空気感まで再現されるので、それが目立つことがありません。
実に豊富な情報量と、見事な空間表現で「展覧会の絵」がリアルに聞けました。
ただ、価格の限界か、電源部分で音が抑制されているのか、完全に開放的な鳴り方にはならず、音の広がりに限界感があります。けれど、この価格で「これ以上」を望むのは酷でしょう。
906の良さは、きちんと作り込まれた製品だけが持っている「音楽的に整った音」と「明るく優しい音質」です。透明感も非常に高く滑らかなその音は、デジタルとは趣の違う「レコードの魅力」をどのように引き出すか、906はその「ツボ」を心得た鳴り方をします。これは、とてもレベルの高いオーディオ機器(フォノイコライザーアンプ)です。![]()


イントロのウインドベルの音は、金属の厚みが増したようなイメージです。フルートもよりしっかりとした音が出ています。
ドラムは、リズムが際立ち、曲の流れにメリハリが出ます。
回路を左右独立にした効果で、チャンネルセパレーションがCDとほぼ同等に感じるくらい大きく向上しています。
電源を別置きに強化した効果で、躍動感やエネルギー感が大きく向上しています。
906では「もう少し欲しい」と感じた、楽器のアタックや押し出し感の強さが向上し、ほぼ文句のつけようのない音が出ています。
ギターも断弦の瞬間のアタック感が向上し、弦を弾く強さの強弱がよりハッキリと伝わるようになりました。ギターの胴に使われる良質なプルースの響きの良さも際立っています。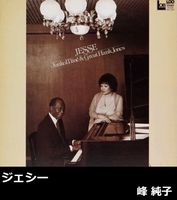
伴奏とボーカルの分離感も向上し、場の空気感が俄然濃くなりました。
906ではステージまでの距離がやや離れているように感じましたが、907では舞台袖で演奏を聞いているイメージです。
より濃密でリアルな音で「ジェシー」が聞けました。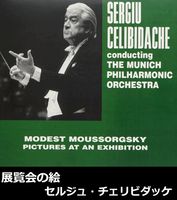
空気感や雰囲気感も群と濃くなり、演奏会がより上質なものへと変化しました。
906で感じた、エネルギーの頭打ち感もほぼ完全に解消しました。個人的には、もう少し「荒々しくても良い」と思いますが、TRILOGYの音は上質で上品。知的で優しく、芯がハッキリと通っている、イギリス上流階級の上品さが伝わります。アストンマーチンのようなサウンドで、ドリーミンが鳴りました。
906の音と907の音は見事に整合し、違うところが全くありません。違っているのは、ステージまでの距離(つまり座席の位置)」だけです。この高度な「チューニング(音決め)」技術には舌を巻くばかりです。
生演奏は、座席が良くなると「確実に音が良くなり」ますが、ステージまでの距離が離れたからといって、演奏が下手に聞こえることはありません。906と907の関係はまさしくその通りです。
レコードを聞いてる感覚に言い換えるなら、906から907にフォノイコライザーアンプを変えると、レコードの録音が良くなった。その表現がぴたりとはまると思います。
906と907の価格差を考えると、906の「お買い得さ」が断然引き立ちますが、907の40万円を切る価格も音質を知れば、十分魅力的に感じられます。
アナログらしい滑らかさと透明感に満ちているので、あらゆるカートリッジとの相性が良さそうですが、最新型の「超HiFi」なカートリッジとの組合せると、どこまで質感の高い音が出るか興味がそそられました。![]()
 QC24P(内蔵トランス)
QC24P(内蔵トランス)
906/907は、トランジスター回路らしい「きまじめで忠実な音」でレコードを鳴らしました。それはそれで魅力的ですが、真空管を使うQC24Pを使うと、演奏がそれらよりもハッキリと「生き生きと」聞こえます。
一つずつの音の変化、ギターやドラムの一音一音の微妙な音色の違いなどが、TRILOGYよりも鮮やかです。
S/N感もそれほど悪化せず、QC24Pも魅力的な音でレコードを鳴らしてくれるフォノイコライザーアンプだと再認識しました。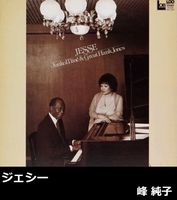
ピアノを弾くハンク・ジョーンスさんの「ピアノのタッチ」も、907よりも鮮やかに感じられます。
907は端正な清潔な音でこの曲を鳴らしました。QC24Pは、お酒の香りが漂うような、よりムーディーな雰囲気でこの曲を鳴らします。
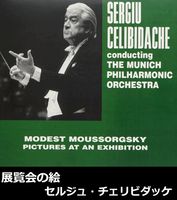
厳密に比較するなら907の音の方が密度解像度が高く、より細部の音までハッキリと再現されているのですが、細かい音まではハッキリと聞き取れない「生演奏を聞いているような雰囲気」には、QC24Pがより近いと思います。
総合評価
私は、明るく開放的で響きの良いQC24Pの音が好きですが、冷静に聞くとそれが「演出されたもの」であることはわかります。それに対して、907には高忠実度で質感が高いという絶対的な魅力、直球ストレートの良さがあります。また、トランジスターと真空管のメンテナンス性を考えても、907とQC24Pの選択はなかなか難しいと思います。![]()
 +
+ 

BV33はQC24Pが内蔵する昇圧トランスよりも、広帯域で過渡特性に優れます。
演奏者の意図が完全な形で伝わる、ほぼ「完璧な音(望み通りの音)」で「亡き王女のパヴァーヌ」が聞けました。もはやレコードを聞いている、オーディオを聞いているという意識は完全に消えています。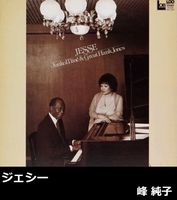
また、内蔵トランスで聞いていたときの「甘いムード」が薄れてきて、スタジオで録音しているリアルさが伝わってきます。
内蔵トランスが感じされてくれた「ライブ感」も魅力的でしたが、BV33が持っているたたずまいの良さ、折り目正しさ(つまり録音された音により近い)魅力、演奏者の技量が上がって感じられる魅力も、抗しがたいものです。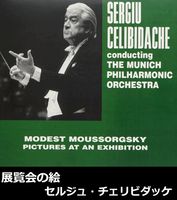
内蔵トランスと比べると、曲調が少し暗く、演奏が重々しく感じられますが、チェリビダッケの指揮する演奏、彼の目指す音楽には、明らかにBV33が近いと思います。
ハーモニーの重厚感、密度感もハッキリ向上しています。
空間の広がりや濁りのなさも、全然違っています。打楽器の迫力、弦楽器の重厚感も大きく向上しました。
内蔵トランスと比較すると、ハーモニー部分での音の濃さ、複雑さが俄然違ってきます。
言い換えるなら、QC24Pが持っていなかった、907の質感の高さが、BV33を使うことで実現するイメージです。
シンセサイザーの音の質、響きの透明感、バックコーラスとの分離感、メインボーカルが伴奏からすっと抜けてくる感じ、すべてが素晴らしい。
内蔵トランスの音は、その個性的な音が魅力的でした。トランスをBV33に変えると、その個性は薄れますが、引き替えに907が持っていた質感の高さがQC24Pで実現するようになります。
あまりに完璧すぎて、面白みがないと言えばそれはそうですが、やはりレコードの検聴に使われていただけあって、説得力のある音を出します。高価な昇圧トランスですが、その価値はあると思います。
一度売り切れましたが、5台ほど作れる材料が入荷したので、近日中に再発売の予定です。それがなくなると、本当の売り切れ(手元に一台は残しますが)になります。コレクターズアイテムとしても、抜群の価値を持つ昇圧トランスです。